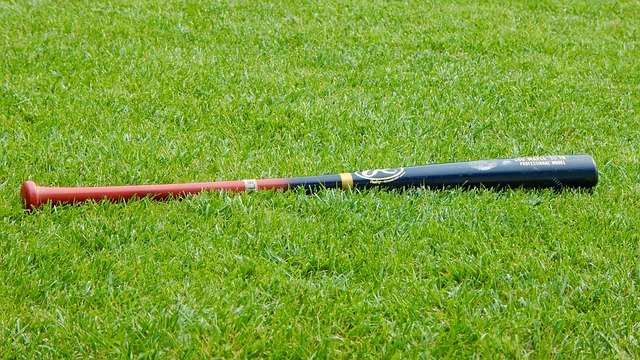
■将来のステージで戦う上で武器になる
横浜高(神奈川)が智弁和歌山(和歌山)を破り、19年ぶり4度目の優勝を果たした第97回選抜高校野球大会。昨年から導入された低反発バットに対する各校の適応が進んでいることが明らかになった。昨春や昨夏の大会では打低傾向が顕著だったが、この大会では得点数・本塁打数ともに増加している。
多くの選手たちは「飛ばないバット」を前向きに捉え、技術向上の好機としているようだ。無理に飛ばそうとするのではなく、コンパクトなスイングを心がけたり、ボールに乗せる技術を磨いたりする意識が高まっている。バックスピンを効かせることや芯に当てる確率を高めることに注力する選手も増えてきた。従来の「飛ばす」という発想から、「運ぶ・捉える」というスキルを磨く方向へと意識が変化しているのが特徴的だ。
木製バットへの対応には体づくりも欠かせない。食事や体づくりから見直す選手、ウエートトレーニングを追加する選手、全身を使って振る意識を持つ選手など、バットの変更がより強靭な身体作りを促すきっかけとなっている。木製バット対応には「身体の準備」も必要で、食事やウエートを見直す良い機会になっているようだ。
ミート力とスイングの質も重視される傾向にある。特殊なバットを使った練習でミート力を高めたり、スイングスピードを上げて投球を見る時間を増やしたりする工夫が見られる。ヘッドを走らせる意識を持つ選手もいれば、ノーステップに変更するなどフォーム自体を改良する選手も出てきた。「芯に当てること」「スイングの質」が何より大事だという認識が広がっている。
注目すべきは、木製バットのメリットを積極的に評価する声が多いこと。力が伝わりやすい、打球が落ちにくいなど、木製バットを肯定的に捉える傾向がある。興味から自主的に木製へ切り替えたケースも少なくない。まずは試してみることで「自分に合うかどうか」を実感できるという考え方が広がっている。
一方で、実戦での適応にはそれぞれの判断がある。金属バットの方が速球に反応しやすいと感じる選手、詰まっても打球が落ちにくいと考える選手、投球を見るために振る力を上げる必要性を認識する選手など、状況に応じてバットを選択する柔軟性も重要視されている。「木製にすべきか」ではなく「自分のスタイルに合うか」が大切で、目的(試合用・練習用)を明確にすることが求められている。
木製バットの導入は、単なる「制限」ではなく「可能性」の拡張と言える。選手たちは振り込みやウェートトレーニングを重ね、ミート力を高めることで、低く強い打球を生み出すようになった。投手起用では分業制がさらに進み、試合展開も先行逃げ切り型が増加するなど、野球のスタイル自体も変化している。
今回の選抜大会で見られた各校の適応と進化は、高校野球の新たな時代を象徴するものだった。道具に頼っているように見えてそうではなく、地道に自分を磨き続ける姿勢こそが、将来どのステージに進んでも活きる武器となる。木製バットという変化を前に、選手たちはより本質的な技術と体づくりに取り組み、高校野球の新たな形を創造している。
 楢崎 豊(NARASAKI YUTAKA)
楢崎 豊(NARASAKI YUTAKA)
